浄土真宗は阿弥陀如来の救いを説きます。
この救いの特徴を「そのままの救い」「無条件の救い」と表現することがあります。
なぜ、これが救いなのでしょうか。

『いい子に育てると犯罪者になります』とは、元立命館大学教授で臨床教育学博士である岡本茂樹さんが書いた新書のタイトルです。
あなたは、にこにこと明るく笑う子どもに声をかけるとしたら、何と言いますか。
ほとんどの人は、「明るくていい子だね」と褒めるのではないでしょうか。
このことに疑問を持つ人はいないでしょう。
しかし、「いい子だね」という、誰もが普通に使っている言葉が、子どもが犯罪者になる「きっかけ」になっている場合があるのです。〈「第1章 明るく笑う『いい子』がなぜ罪を犯すのか」より〉
新書らしい挑戦的なタイトルですが、内容は非常に理路整然として興味深く、子どもを持つ親や人を教育する立場にある教師、役職者だけでなく、生きづらさを抱える人にも多くの示唆を与えるオススメの一冊です。

刑務所での更生支援に携わった筆者は「受刑者にかぎれば、彼らの幼少期の家庭環境は100%不遇であった」と述べます。
親が子どもの傷ついた心を受け止める存在ではなかったとき、子どもは素直な感情を出せなくなり、偽の感情を出すことで本当の感情(否定的感情)を封じ込めます。そうして自分の感情に鈍感になると、他者の感情も分からなくなります。
受刑者が更生するためには、本人が幼少期に感じていたはずの悲しみやつらさといった否定的感情を自分自身で「感じること」から始めないといけません。
悲しいときは悲しい気持ちになります。つらいときはつらい思いを感じます。自分の感情を素直に感じ、表現できるようになること──「そんなことは簡単ではないか」と言われそうですが、受刑者にはそれができません。幼少期にそれが許されない環境であったためです。

〈photo by HORIPRO〉
親の関わり方について重要さを示すために、筆者は演出家・宮本亜門さんを取り上げたドキュメンタリーを生徒に見せるそうです。

宮本亜門さんは、1958年1月に新橋演舞場の近くで喫茶店を営む父親と、松竹歌劇団専属のダンサーであった母親との間に生まれました。
本名は宮本亮次といいます。趣味は仏像鑑賞で、小遣いを貯金しては京都や奈良を旅していました。

港区立白金小学校から玉川学園へ進学しますが、高校1年生のときに不登校になり、約1年間ひきこもり生活を送り、その間に自殺未遂をしています。
酔っ払った父親に日本刀を突き付けられたことがきっかけで、宮本さんは母親と病院に行くことを約束。1年生の終わりに慶應病院の精神科に通院を始めます。
そこで精神科医と出会い、学校に復帰できるまでに回復します。その後は演劇を学び、ダンサーとして活躍し、名前を亮次から亜門へと改名し、日本だけでなく海外でも演出家として注目を浴びています。

さて、宮本さんは高校1年生のときに不登校になったそうですが、なぜでしょうか。これはドキュメンタリー内の本人の語りと再現ドラマから明らかになります。

宮本さんが幼少期を過ごした場所は、新橋演舞場近くの喫茶店です。日本舞踊や歌舞伎の演者が多く来る店でした。
宮本さんは母親と一緒に演舞場に注文の品を配達することがあり、舞台の奈落で多くの役者を間近に見ていました。
そのような環境にいたため、宮本さんも日本舞踊に興味を持ち、幼少期のとき藤間流日本舞踊を習うことになります。
「事件」は、そのときに起きました。
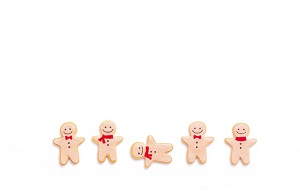
稽古が終わってから学校に行った宮本さんは、いじめに遭います。首の周りに白粉(おしろい)がついていたので、それを見た子どもたちが「男のくせに化粧している。女だ、女だ!」と取り囲んだのです。
「これは白粉だよ!」と反論しても、そんな言葉は子どもたちには通用しません。ひどく落ち込んで家に帰った宮本さんは、「踊りをやめたい」と母親に告げます。
以下は、再現ドラマで交わされた亮次と母親の会話です。
「お母さん……踊り、やめる」
「なんで?」
「女みたいってバカにされた」
「バカねえ。何にも恥ずかしいことないじゃない。みんなの方が変なのよ。芸ごとがわからない連中は放っておきなさい。いいわね。ほら、元気出して。笑って」

母親に言われるがままに、それまで暗い表情だった宮本さんは無理やり笑顔を作りました。
「笑顔でいること」は母親のしつけの一環だったのです。忙しく厳しい母親でしたから、そうしなければ、自分は愛してもらえない、見捨てられてしまうかもしれない……という不安もあったのでしょう。
しかし、笑顔でいることが、自らを苦しめ、ひきこもり、そして自殺未遂にまで追い込む原点となっていたのです。
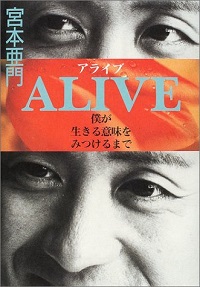
宮本さんは当時のことを自伝で「『日舞を習うことは、普通とは違うことなんだ。みんなには言わないようにしよう』と、心に決めた。それまでは、いたって天真爛漫な子どもだったのだが……」と語っています。
「ありのままの自分」でいられなくなった瞬間です。

岡本先生はドキュメンタリーを生徒に見せたあと、簡単な演習を行うそうです。
「前述の亮次と母親の会話について、もしも生徒の皆さんが母親(あるいは父親)だったら、亮次の言葉に対して、何と言いますか」
皆さんも考えてみてください。もちろん、正解はありません。
ある男子学生は答えます。
「踊りをやめたいのなら、やめてもいいよ。亮次の好きにしていいよ」
一見、物分かりのいい回答のように見えます。ですが、亮次は踊りをやめることを母親に認めて欲しかったのでしょうか。
ある女子学生が答えます。
「お母さんは亮次の踊る姿が好きだなぁ。やめたいと思う気持ちになることもあるけど、お母さんは続けて欲しいなぁ」
踊りを続けて欲しいという親の願いがこもった言葉です。ただ、こう言われると、亮次は何も言い返せなくなってしまいます。

考えるポイントは、亮次はこのとき「母親にどうしてほしかったのか」ということです。
亮次が「踊りやめる」と言った背景には「女みたいってバカにされた」ことがあります。
子どもはストレートに感情を表現するのが苦手です。
したがって、子どもの言葉の裏に隠されたメッセージを大人は読み取らなければなりません。

亮次の言葉は、いじめられたことで悲しかった、つらかった、苦しかった思いがいっぱい詰まっています。
子どもがいじめられたことを親に言うのはものすごい勇気が必要です。ヘルプの信号を出しているのです。
だからこそ、励ましや助言は「正論」となって、逆に子どもの心を閉ざさせることになります。
親はただ亮次の否定的感情を受け止めればいいのです。
そうすれば、亮次はその後に続く苦しい思春期を過ごさずにすんだのかもしれません。

ちなみに「正解はない」のですが、筆者の岡本先生が自分なりの正解を「あとがき」の最後に記してくれています。後ほど紹介します。

なぜ亮次はひきこもりになったのかを確認しておきます。
亮次の母親に愛情がなかったわけではありません。
むしろ、母親は強い愛情を亮次に注いでいました。
そして、亮次も母親の愛情を感じていました。
問題は、母親の子どもへの関わり方です。

苦しくても悲しくてもつらくても、笑顔でいることを母親は亮次に求めたのです。
それが、亮次に本当の感情を抑圧させることになりました。
結局、亮次は苦しみを「笑顔」で封じ込め高校生になってから、不登校、ひきこもり、そして自殺を試みるまでに追い詰められていったのです。

宮本さんが慶應病院の精神科に通院したことは述べました。
医師は亮次に対して、指示や助言など一切しません。
宮本さんは「すごく気さくな人で。な~んにも壁がなくて、ある意味拍子抜けするくらいの方で。ただただ聴いてくれる人で。それがうれしくて、通っちゃったんですよね」と語ります。

不登校であれ、ひきこもりであれ、犯罪であれ、およそ世間一般で問題行動といわれる行動を起こした人を支援するために必要なのは、その人を理解し、寄り添って考えてくれる存在です。
「しんどいことが続いたんだね」「つらかったんじゃないか」「寂しかったよね」といった言葉を返しながら、共に原点を探っていく「共同作業」が支援そのものになります。
自分のことを分かってくれようとする人がいて、その人の力を借りて抑圧していた自分の否定的感情を解放できたことで、亮次は立ち直っていきました。

この時のことを宮本さんは自伝の中で「『人が認めてくれる』『こんな僕でもいいんだ』という安堵感が、診察を受けている間にじわじわ体に広がっていったのです」と書いています。
「ありのままの自分」を認めてくれる人がひとりでもいたから、宮本さんの命は救われました。〈参考・引用『いい子に育てると犯罪者になります』岡本茂樹〉
あとがき
幼いとき私は、宮本亜門さんのようにいつも笑っている子どもでした。
気持ちが落ち込んでいるときも、友だちから「今日はどうしたの? 何かあったの?」と言われると「何もないよ」と言って笑顔を「つくって」いました。笑うことが当たり前になっていたのです。
そして当時は、笑うことが自分自身を苦しめることになるなど思いもしませんでした。
心理学を学び、受刑者と関わるなかで、幼いとき私はなぜ笑っていたのか理由がはっきりしました、
私は母親を喜ばせたかったのです。
私の父親は私が幼稚園のときに亡くなり、私は母親に育てられました。
私は長男だったこともあって、周囲の者から「お前がしっかりして、将来は母親を支えていけよ」とよく言われました。
幼いときの私は、そう言われることが「当たり前」になっていました。
そして、幼いときの私の「母親を支える方法」にひとつは、笑顔でいることだったのです。
笑顔でいれば母親も喜んでくれる──そう思っていました。
逆に言うと、笑顔でいないと母親は悲しむと思い込んでいました。
自分で勝手に「母親に愛されるための条件」をつくっていたのです。
そういう生き方が苦しみを生むことに気づくのは、かなり後になってからでした。
中学生の頃は、「将来はいい会社に入って、母親を楽にしてあげないといけない」と思っていました。一生懸命に勉強もしました。
しかし結果にはつながりませんでした。それがストレスになっていたのでしょう。
学校で私はイライラを他の生徒にぶつけるようになりました。
教師からすると、ちょっとした「問題生徒」だったのです。
当時は強がっていたようにも思います。
喧嘩などできないくせに、強そうな相手に挑発的な言葉をかけていました。
今でも忘れられないことがあります。
ある日、数学の教科の先生が休んで、自習の時間になりました。
自習の時間には監督の先生が来ます。若い女の先生でした。
自習時間は「遊びの時間」のような感覚です。
まじめに勉強していない私を見た監督の先生は、私の隣に座っていた友だちに対して、「岡本君のようになったらダメよ。君はちゃんと勉強しなさいね」と言ったのです。それも私の目の前で。
その言葉を聞きながら私は、顔は笑っていながら、内心ひどく傷ついていました。
その後に、私は明らかな問題行動を起こしました。
その若い女性の先生のテストでカンニングをしたのです。
「魔が差した……」と言いたいところですが、理由があります。その先生が大嫌いになったからです。
その先生のテストにかぎって、私はまじめに勉強してテストを受ける気持ちを完全になくしていました。
しかし、間の抜けた話ですが、試験中に教科書をこっそり出しているところを、あっけなく見つかりました。
当然のことながら、放課後、母親が呼び出されることになります。
そのときの私の担任の先生は、英語を教える若い男性の先生でした。
先生と母親だけが話し合いました。私がひとり教室で待っていました。
ふたりが話し終えた後、帰り道で私は母親から厳しく叱られることを覚悟しました。
ところが、母親は何も言わなかったのです。
それどころか、「今日の晩御飯は何にする?」と尋ねてきたのです。
そのとき私は「なぜ叱らないんだろう?」と不思議で仕方がありませんでした。
それからしばらくして、担任の先生が「無理しなくていいからな」と私に声をかけてくれたのです。そのとき私がすべてを理解しました。
母親を呼び出したとき、担任の先生は私が日ごろ感じていたストレスを母親に話してくれたのだろう、と。
私は担任の先生の「愛情」を感じました。
同時に叱らなかった母親の思いも改めてうれしく感じました。
「今の自分でいい」と思えた瞬間でした。それ以降、私は「問題生徒」ではなくなりました。
罰を与えると人は悪くなる。愛を与えると人は良くなる。人は、人によって傷つけられる。[中略]
最後に、第1章の宮本亜門さんとお母さんの会話の演習ですが、「私なりの正解」を記しておきます。
それは「何かしんどいことがあったの? どんなことがあってもお母(父)さんは君の味方だから」と言って子どもを抱き締める、です。
これが私が親に求めたい愛情表現の言葉です。

幼少期に無条件の愛情を受けたかどうかは、その後の人格形成に大きく左右する……自己心理学では定説となっています。
もちろん、それだけで人間を語るのは危ういのですが、「ありのまま」「無条件」は私たちが根源的に求めている世界といってもいいと私は考えています。

お釈迦さまや親鸞聖人は早くに母親を亡くしています。
もしかしたら、人間同士の営みでは決して埋めることができない究極の母性を求めて出遇ったのが「そのままの救い」「無条件の救い」と表現される阿弥陀如来の救いだったのかもしれません。

生きとし生けるものは、誰もがありのままに認められる世界を求めていて、その世界が『仏説無量寿経』に説かれていることを親鸞聖人は明らかにしてくださいました。