1918(大正7)年、芥川龍之介が発表した『蜘蛛の糸』。
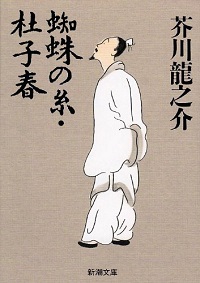
お釈迦さまがある朝に極楽をぶらぶら歩いていました。蓮池を通して下の地獄を覗くと、罪人たちが苦しんでいる中にカンダタ(犍陀多)という男を発見します。
カンダタは殺人・放火などを働いた大泥棒ですが、過去に一度だけ善い事をしたことがありました。それは林で小さな蜘蛛を踏み殺しかけて止め、命を助けたことです。
そのことを思い出したお釈迦さまは、1本の蜘蛛の糸を地獄へ下ろしてカンダタを救い出すことにしました。
暗い地獄で天から垂れて来た蜘蛛の糸を見たカンダタは「この糸をのぼれば地獄から出られる」と考え、糸につかまってのぼり始めます。
ところが途中で疲れてふと下を見下ろすと、数多の罪人たちが自分の下から続いてくるではないですか。
このままでは重みで糸が切れてしまうと思ったカンダタは、下に向かって「この糸は俺のものだ!下りろ!」と喚きました。すると蜘蛛の糸がカンダタのぶら下がっているところから切れ、カンダタは再び地獄の底へ……。
自分だけ助かろうとし、結局元の地獄へ堕ちてしまったカンダタを浅ましく思ったのか、それをご覧になっていたお釈迦さまは悲しそうな顔をしてまたぶらぶらと歩き始めたのでした。(全文はコチラ)

極楽(浄土)は阿弥陀如来の国であるにも関わらず、お釈迦さまがいるのはどうしてでしょうか。仏さまがぶらぶらして、救済方法が気まぐれなのも疑問です。

というのも、この物語はお経を根拠にしたものではありません。芥川龍之介自身の解説がないため諸説はあるようですが、ドイツ生まれでアメリカで活動した哲学者のポール・ケーラスが1894年に発表した「カルマ」という作品がルーツのようです。
1898(明治31)年に仏教学者の鈴木大拙が「カルマ」を翻訳して『因果の小車』を出版しました。その本に収録されている「蜘蛛の糸」の一節に芥川龍之介が手を加えた……といわれます。

『因果の小車』は、インドを舞台にした作品です。とある豪商と、豪商の召使いから山賊へとジョブチェンジした男の人生を描いた短編作品です。
物語の終盤で、山賊の男は仲間に裏切られて致命傷を負います。通りかかった僧侶によって介抱されながら、山賊の男は裏切りを自業自得と受け入れました。
しかし、死後に受けるさらなる裁きや報いに恐怖した男は、僧侶に対して解脱の道を求めます。
僧侶は「我執の妄念(煩悩)」を離れることこそが解脱の道であると示しました。その際にカンダタという極悪人が登場する喩え話を説きます。それが『因果の小車』には「蜘蛛の糸」という節として収録されています。
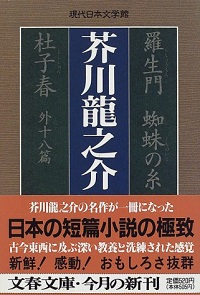
つまり、この物語で登場する僧侶の説法を材源として芥川龍之介の「蜘蛛の糸」は作られたのです。

『因果の小車』の「蜘蛛の糸」では、お釈迦さまは極楽ではなく閻浮提(この世)でさとりを開かれた直後という状況で登場します。

さとりを開いたお釈迦さまの光明は地獄で永きにわたって苦しんでいたカンダタの元にも届きました。
カンダタは、お釈迦さまに「私は罪を犯しましたが、やり直せるのであれば今度は正しい道を歩きたいと思っています。どうにかしてこの苦しみの世界から救ってください」と懇願します。
お釈迦さまは答えます。「悪い行いをすれば悪い報いを受け、善い行いをすれば善い報いを受ける。これが“カルマ”というものです。あなたが地獄に墜ちるのは当然のことのように思います。あなたは何かひとつでも善行をしたことはありますか?」
カンダタは黙ります。生まれついての極悪人にはそんな心当たりはありませんでした。
しかし、お釈迦さまがカンダタの過去を見通すと、蜘蛛を助けた過去がありましたので、蜘蛛の糸によってカンダタを救うことにします。
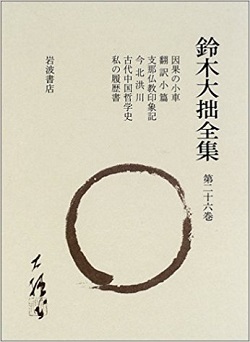
『因果の小車』に描かれているカンダタは、お釈迦さまとの対話を通じて自分がのぼっている蜘蛛の糸がさとりに向かう道であることを理解し、自分自身もさとりを求めて糸をのぼります。
「去れ去れ!此の糸はわがものなり!」
というカンダタの台詞については芥川龍之介版と同じです。
しかし、糸の行き先と意味を知っているかいないかで、この言葉の受け取り方は大きく変わります。
カンダタは、自らが求めた一切衆生を救う道を「我執の妄念(煩悩)」によって否定したのです。
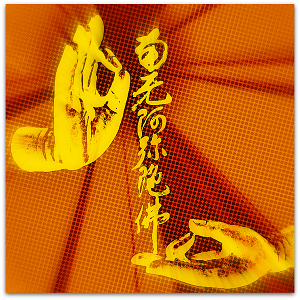
私たちもまた、浄土へ生まれると一切衆生を救う仏さまとなります。

しかし、これは煩悩を持つ凡夫にはなかなか理解できません。普通の人間はすべての人を救いたいとは考えないからです。
好きな人ならともかく、嫌いな人や苦手な人を救うために一生懸命に努力することは不可能といっていいでしょう。
他人の足を引っ張ったり、蹴落とすことに一生懸命になることはできるかも知れませんが、すべてのものを救う仏になるといわれても理解できないのです。
仏さまのさとりの領域と、私たち凡夫のすがたに大きな隔たりがあることだけではなく、さとりへ自ら歩んでいくことの困難さを改めて痛感します。[続く]
〈参考・引用『季刊せいてん no.119』本願寺出版社〉