罪おもく、障ふかく、心くらく、解すくなからんにつきても、いよいよ仏の本願をあふぐべし。そのゆへは弥陀の本誓はもと凡夫のためにして、聖人のためにあらずといへる文によりてなり。あふぐべし、信ずべし。(「耳四郎を教化したる御詞」)
罪が重く、仏道を歩む上での支障が深く、闇のように心は暗く、理解力が乏しいなどということを思うにつけて、それだからこそ、いよいよ阿弥陀仏の本願を仰ぎ、尊びなさい。その所以はというと、阿弥陀仏の本願は、本来凡夫のために建ててくださったものであり、聖人のためではないというご文があるからである。まことに仰ぎ尊び、信じないわけにはいかない。
法然聖人が耳四郎を教化された経緯は、覚如上人の著された『拾遺古徳伝』に詳しく記されています。

昔、摂津の国(現在の大阪)の幣島(みてくらじま)に耳四郎とあだ名された粗悪な人間がいて、あちこちで盗みなどの悪事をしていました。その耳四郎が、あるとき京都に上り、盗みに適した場所を探していたところ、夜に法座が予定されている寺を見つけます。人々が多く集まる所は最適だと考え、御堂の下に隠れ、みんなが寝静まるのを待っていました。
その寺は、法然聖人の弟子、信空上人の寺で、その日は法然聖人のご法談の日でした。耳四郎は縁の下に隠れていただけで、聴聞しようというつもりなどなかったのですが、耳四郎といわれるくらいなので、耳も大きく聴力も並外れていたのでしょう。上から聞こえてくる聖人の説法に聞き入ってしまい、皆が寝静まり、「さあ、これから仕事だ」という時間になっても、先ほどの詞が耳から離れず、朝を迎えました。明るくなって弟子たちに発見された耳四郎は「昨晩ご説法のお聖人に会わせてほしい」と頼み、お出ましになった法然聖人に「自分のような者でも救われますか」と尋ねたのです。

そのとき、法然聖人は
宿縁もともありがたしとて、〈中略〉手をとりて慇懃(おんごん)にとききかせたまふ
「宿縁もっとも有り難い」と仰せになって、〈中略〉法然聖人自ら手にとって、丁寧にご説法になられた
と伝えられています。

覚如上人は『拾遺古徳伝』にこの経緯を記された後、
この耳四郎は至極の罪人、悪機の手本といひつべし。今時の道俗、たれのともがらか、これにかわるところあらんや。〈中略〉つくるに強弱ありといへども、三業みなこれ造罪なり。をかすに浅深ありといへども、一切ことごとくそれ妄悪なり。〈中略〉つくるもつくらざるもみな罪体なり。おもふもおもはざるも、ことごとく妄念なり。〈『真宗聖教全書』3・712〉
この耳四郎という者は、非常に重い罪を犯した者であり、救われがたい存在(悪機)の典型であると言ってよい。いま現在の出家の者も、在家の者も、誰もみな耳四郎と全く変わらない。〈中略〉行いに軽重(強弱)の違いはあるけれども、身・口・意の三業すべてが罪をつくるものである。罪を犯すにも浅いもの深いものの違いはあるが、すべてがとらわれによる悪の行いである。〈中略〉造るも造らないも、皆本質的には罪で、思うも思わないもことごとく迷いの心によって生み出されている。
と続けておられます。
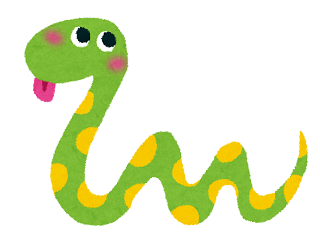
例えば「マムシ」は、人を咬んだ時だけが毒蛇で、咬まなければ毒蛇ではないと言えないように、悪縁にあえば、どんな恐ろしいことをするか知れない悪の本性を持っているものを「煩悩具足の凡夫」というのです。
「マムシ」は一度も人を咬まずに終わることがあるかも知れませんが、人間は毎日さまざまに人を傷つけ、自分を傷つけながら生きているのです。
たとえ今まで殺人や強盗をはたらかなかったとしても、それはただ幸いにして悪縁にあわなかっただけでのことです。私の本性が立派だったからではありません。
そしてこれからも、どんな縁にあって、どんな振る舞いをするか、まったく保障のできないのが凡夫というものの不気味さなのです。
「つくるもつくらざるもみな罪体なり。おもふもおもはざるも、ことごとく妄念なり」という言葉に、身震いするような恐ろしさを感じます。
耳四郎の回心を聞いて、同じ煩悩を抱えている罪悪深重の私が、大悲本願の正しきお目当てであり、「たえず如来のみ心を痛みたてまつっている身であること信知するものは、かかる身を救うて二度と罪業を犯すことのない仏たらしめよう」と誓われた大悲の本願を仰いで、日々の生活を厳しく自誡していかねば、仏祖に申し訳がないと思います。

「正信偈」に「一切善悪凡夫人」とあるように、善人も悪人も等しく凡夫です。
『御文章』「易往無人章」には
智慧もいらず、才学もいらず、富貴も貧窮もいらず、善人も悪人もいらず、男子も女人もいらず、
とあります。
善人とか悪人とか、男とか女とか、好きとか嫌いとか、役に立つとか立たないとか……そうした価値観はすべて凡夫の物差しです。

阿弥陀如来は「十方衆生」を等しく救いの目当てとされています。凡夫の物差しにこだわってばかりでは、仏意が疎かになってしまいます。
【参考文献】
『真宗聖教全書』
『季刊せいてん no.109』
『聖典セミナー 歎異抄』