【なかに含む大蔵経】
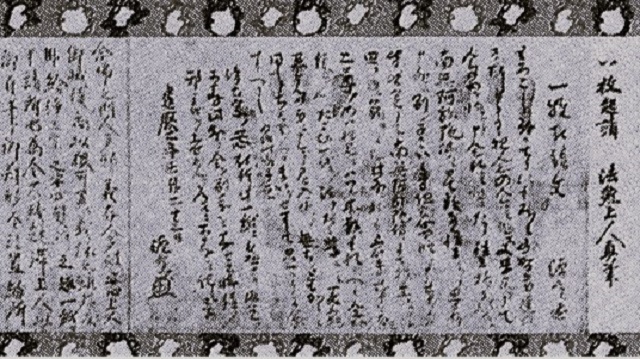
『一枚起請文』の特徴は、文体の簡潔にして流暢なことです。おそらく、法然聖人ご自身が繰り返し口に出して仰り、磨き上げていかれた言葉なのではないでしょうか。それはちょうど蓮如上人の作と伝えられる『領解文』を彷彿とさせるようであります。

実は『一枚起請文』には黒谷金戒光明寺に伝えられる一本の他にも、いくつか異本が伝えられています。
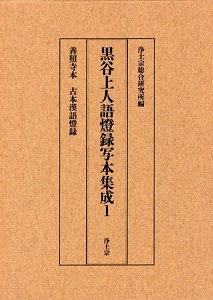
その一つに了慧道光の編集になる『黒谷上人語灯録』巻第十五(『和語灯録』巻第五)所収の「諸人伝説の詞」(『真聖全4』p.678)があります。

この異本は聖光房弁阿上人(鎮西派の祖。現在の浄土宗での第二祖)によって伝承されたものです。内容はほぼ同じですが、表現がやや異なります。
又上人のゝ給はく、念佛往生と申す事は、もろこしわが朝の、もろもろの智者たちの沙汰し申さるゝ觀念の念佛にもあらず、又學問をして念佛の心をさとりとほして申す念佛にもあらず、たゞ極樂に往生せんがために南無阿彌陀佛と申て、うたがひなく往生するぞとおもひとりて申すほかに、別の事なし。たゞし三心ぞ四修ぞなんど申す事の候は、みな南無阿彌陀佛は決定して往生するぞとおもふうちにおさまれり。たゞ南無阿彌陀佛と申せば、決定して往生する事なりと信じとるべき也。念佛を信ぜん人は、たとひ一代の御のりをよくよく學しきはめたる人なりとも、文字一もしらぬ愚癡鈍根の不覺の身になして、尼入道の无智のともがらにわが身をおなじくなして、智者ふるまひせずして、たゞ一向に南無阿彌陀佛と申てぞかなはんずると。(『浄土真宗聖典全書(六)補遺篇』「和語燈録」p.606)
この弁阿上人の伝承の異本は、源智上人に与えられた黒谷金戒光明寺本に比べると、表現としてまだ硬い印象を受けます。
もちろん、これはこれで丁寧で行き届いた表現が取られていると言うことができ貴重なのですが『一枚起請文』という題号も付いておらず、本文にも起請文ならではの誓いの言葉が見られません。
恐らくは黒谷金戒光明寺本よりも、時期的に先行する法然聖人のお言葉を伝えているものと考えられます。
こうした異本の存在からも『一枚起請文』のお言葉は、源智上人の要請をもって臨終に初めて考え出されたものではなく、法然聖人の長年の御説法なかで練り上げられたお言葉であったことが知られます。

江戸時代の嵯峨天龍寺の桂州和尚道倫禅師(臨済宗)は
だれがいう一枚の紙 なかに含む大蔵経 天外に出頭する者 はじめて知らん この語のかんばしき
いったい誰がたった一枚の紙などと言うことができようか。この短い言葉の中には深遠な釈尊一代の経の説法がすべて籠っている。仏教の極意に達した者にして、はじめて知ることができるであろう。この『一枚起請文』がいかに香り高いものであるかを。
と述べられたそうです。

わずか一枚の紙に収まる文章ですが、そのなかに釈尊一代の教えの結論が明かされているといえるのでしょう。