「袈裟(けさ)」は一般的にお坊さんが身につける衣服をいいます。

袈裟の原語は古代インド語であるサンスクリット語「カーシャーヤ(kāṣāya)」です。
インドでは赤褐色(インド茜色)を示し、中国で「壊色(えじき)」と翻訳されました。つまり、元々は衣服ではなく色を表す言葉であったようです。

「壊色」とは、鮮明な原色を避けた色です。青・黄・赤・白・黒の五正色、及びそれぞれの中間色のようなハッキリとしていない色(不正色|ふしょうじき)をいいます。

具体的には「木蘭(もくらん)色」「松葉色」(青黒色|せいこくしょく)「泥色」(黒・ねずみ色)などです。
これらは「濁色」と呼ばれ、当時のインドの人たちが好まない汚い色であったといいます。
「青黒色」は銅につく錆の色ですし、当時の「黒色」は泥のような色でした。

興味深いのは「木蘭色」です。染め方によってかなりバラつきがあるようですが、一見すると趣のあって渋い色のように感じられます。
もちろん、これは現代の日本人である私の感覚であって、当時のインドの人たちからするとそうでなかっただけかも知れません。
木蘭色はインドに自生している木蘭樹の樹皮で染めた色とする本もありますが、調べたところによればインド北部からビルマの森林に自生する「ミロバラン」という樹木の実によって染めた色と考える説が有力です。

ミロバランは別名を「呵梨勒(かりろく)」といいます。
正倉院に納められている60種類の薬物が記された「種々薬帳(しゅじゅやくちょう)」にその名前があることから、染料としてだけでなく、漢方薬としても用いられていたことが分かります。

実はクチナシやウコンなど、漢方に使われる植物は染料として用いることも多いです。
薬である漢方と服を彩る染料の関係を考えるときに、薬を飲むことを「内服」「服用」「服薬」ということが思い出されます。
ここに「服」という文字が出てくるのはどうしてでしょうか。
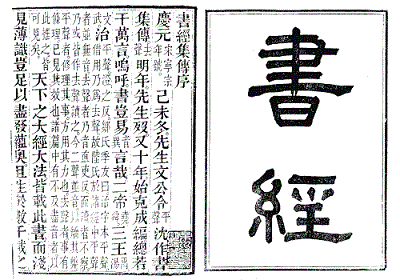
中国最古の歴史書である『書経』には、「草根木皮は小薬なり。鍼灸は中薬なり。飲食、衣服は大薬なり」という言葉があります。「薬」と「服」の関係がうかがえるのではないでしょうか。
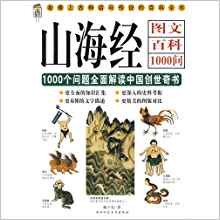
他にも中国古代(前4世紀 - 3世紀頃)の風水書・地理書である『山海経(せんがいきょう)』では、各地の動物(270種)・植物(約150種)・鉱物(約60種)といった産物が挙げられると同時に天然薬物に関する記述があります。
「ここにはこんな生き物がいて食べたり身につけるとこんな効果がある」と様々な事例が紹介されています。そのなかに「服用」の語があり、これが語源であろうといわれます。
他にも薬を飲むことを「内服」、身につけることを「外服」とする文章もあるようですが、見つけることはできませんでした。

「服」には「身につけて着るもの」以外にも、「服従」のように「つき従って離れない」といった意味があります。
ここからは推測の域を出ませんが、薬の効果は外側から内側から服のように私たちにくっついて、その効用に従わせることから、薬を使うことを「内服」とか「服用」と言うのではないでしょうか。

参考までに『漢方と民間薬百科』の一節を紹介します。
薬のはじまりは、おまじない(呪術)と一緒にはじまっている。中国の戦国時代にできたものでと云われている「山海経」という書物には、次のようなことが書いてある。
古代人は、病気を悪魔のしわざと信じた。そこで、病気にならないためには、悪魔を体の中に入れないようにすればよいわけだから、悪魔がいやがるであろう、グロテスクなものや、いやな臭気のあるものなどを、肩にかけたり、腰にぶらさげたりした。
外出するときや旅行に出かけるとき、このようにしておれば安全であると信じた。これが今日の「お守り札」の始まりである。
こうして体の外側に付けることを「外服」といった。服とは、身体につけることである。
ところが病気になった場合は、悪魔が身体の中に入ったと言うことである。追い出さなければならないが、外服では役にたたない。悪魔を追い出す力のあるものを内服しなければならない。
薬を飲むことを内服というのは、これから起こったのである。
このように、「山海経」に書かれたものは、薬というよりは、むしろ呪術の道具として用いられたものだが、これが長い年月の経過によって、だんだん薬としての形態をととのえるようになたのである。

袈裟の話しから大きく逸れてしまいました。
「袈裟」は「壊色」を意味していて、「木蘭色」などがそれにあたります。
木蘭色は漢方としても用いられたミロバランという樹木の実によって染められた色です。
『病気の迷信』という本には薬(漢方)と服(染料)の関係について、次のように書かれていました。
第一に、昔は服が包帯の代わりをしていたということです。時代劇などで足に切り傷をした場合、着物の袖や手ぬぐいを切り裂き、傷口に巻いている場面を見たことがあるでしょう。
第二として、昔は着物や手ぬぐいを染める染料に漢方薬を使っていました。旅先でケガをしたり、発熱など急な病気になった場合、現在のように救急車を呼べるような時代ではありませんでした。
そこで着物や手ぬぐいの染料が漢方薬の役目を果たし、一石二鳥になっていたのです。発熱したとき、解熱作用のある漢方薬を染料にした着物の袖の一部を切り裂き、お湯で煎じて飲んだり、ケガをしたとき止血作用のある漢方薬を染料にした手ぬぐいの一部を切り裂き、傷口に巻いたりして使われていました。
薬と服にはこのような関係があったので「服」の字が薬に関する言葉として使われるようになったのです。
出典がないため眉唾な話ではありますが、「薬の効果のある植物が染料として袈裟に使われている」と考えるのは面白い推察ではないでしょうか。
ちなみに美しい色の布が手に入った場合でも、わざわざ壊色に染め直してから袈裟に仕上げます。
これは染色(ぜんしき)と呼ばれ、袈裟を作るときのルールのひとつです。
合掌