近隣寺院の坊守さまがご往生されました。
私は会係(えががり)として、法要儀式の準備に携わることになり、責任者である会奉行(えぶぎょう)の先輩の指示に従って法要儀式を作ります。

今回は『御文章』「大聖世尊章」の拝読という大きな仕事をいただきました。
長年にわたってお世話になった坊守さまの仏事ですから、完璧に読みたいものです。

『御文章』の拝読は「読み聞かせ」を目的としているため、読み手は内容を完璧に理解していなければいけない……と、浄土真宗本願寺派の法式専門学校である勤式指導所で習いました。

お通夜で拝読する『御文章』は基本的に「大聖世尊章」であると『葬儀規範』には記載されています。
本文と現代語訳は次の通りです。
それ、つらつら人間のあだなる体を案ずるに、生あるものはかならず死に帰し、盛んなるものはつひに衰ふるならひなり。さればただいたづらにあかし、いたづらにくらして、年月を送るばかりなり。これまことになげきてもなほかなしむべし。このゆゑに、上は大聖世尊(釈尊)よりはじめて、下は悪逆の提婆にいたるまで、のがれがたきは無常なり。
しかれば、まれにも受けがたきは人身、あひがたきは仏法なり。たまたま仏法にあふことを得たりといふとも、自力修行の門は、末代なれば、今の時は出離生死のみちはかなひがたきあひだ、弥陀如来の本願にあひたてまつらずはいたづらごとなり。しかるにいますでにわれら弘願の一法にあふことを得たり。このゆゑに、ただねがふべきは極楽浄土、ただたのむべきは弥陀如来、これによりて信心決定して念仏申すべきなり。
しかれば、世のなかにひとのあまねくこころえおきたるとほりは、ただ声に出して南無阿弥陀仏とばかりとなふれば、極楽に往生すべきやうにおもひはんべり。それはおほきにおぼつかなきことなり。
されば南無阿弥陀仏と申す六字の体はいかなるこころぞといふに、阿弥陀如来を一向にたのめば、ほとけその衆生をよくしろしめして、すくひたまへる御すがたを、この南無阿弥陀仏の六字にあらはしたまふなりとおもふべきなり。
しかれば、この阿弥陀如来をばいかがして信じまゐらせて、後生の一大事をばたすかるべきぞなれば、なにのわづらひもなく、もろもろの雑行雑善をなげすてて、一心一向に弥陀如来をたのみまゐらせて、ふたごころなく信じたてまつれば、そのたのむ衆生を光明を放ちてそのひかりのなかに摂め入れおきたまふなり。これをすなはち弥陀如来の摂取の光益にあづかるとは申すなり。または不捨の誓益ともこれをなづくるなり。かくのごとく阿弥陀如来の光明のうちに摂めおかれまゐらせてのうへには、一期のいのち尽きなばただちに真実の報土に往生すべきこと、その疑あるべからず。このほかには別の仏をもたのみ、また余の功徳善根を修してもなににかはせん。あら、たふとや、あら、ありがたの阿弥陀如来や。
かやうの雨山の御恩をばいかがして報じたてまつるべきぞや。ただ南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と声にとなへて、その恩徳をふかく報尽申すばかりなりとこころうべきものなり。あなかしこ、あなかしこ。
さて、よくよく人間のはかないありさまを考えてみますと、命あるものは必ず死に帰し、盛んなる者もついには衰えるのが世のさだめです。ですから、ただむなしく日々を過ごし、無意味に暮らして年月を送るばかりであるのは、どれほど深く嘆いても嘆きつくすことはできません。「大聖世尊」と人びとに仰がれたお釈迦さまをはじめとし、悪逆のかぎりを尽くしてお釈迦さまに反逆した「提婆達多」に至るまで、いかなる人も逃れることのできないのが無常の道理です。
そうであるからこそ、人間に生を受けることも、仏法に遇うことも、滅多にない有り難いことなのです。たまたま仏法に遇うことができたとしても、現在は末法の時代ですから、自力の修行によって生死の迷いを離れてさとりを開くことはできないので、阿弥陀如来の本願に遇わせていただかなければ意味がありません。ところが、すでに私たちは、「弘願の一法」といわれる大いなる本願に遇うことができました。ですから、ひとへに願うべきは極楽浄土であり、たのみとすべきは阿弥陀如来です。このようなわけで、ただ本願を信じて念仏を申すべきであります。
ところで、世間のほとんどの人は「ただ声に出して南無阿弥陀仏と称えさえすれば、極楽浄土に往生ができる」と思っています。それは大きな思い違いです。
では、南無阿弥陀仏の六字にはどのような意味があるのかといえば、「阿弥陀如来におまかせするならば、阿弥陀如来はその人のことをよくご覧になって、必ずお救いくださる」という阿弥陀如来のおこころそのものをあらわしています。その阿弥陀如来の救いのはたらきそのものが「南無阿弥陀仏」の六字の名号です。
では、その阿弥陀如来の本願を、どのように信じて後生の一大事の救いにあずかるかというと、何も思い悩むことなく、あらゆる自力の行を捨てて、ただひたすらに阿弥陀如来の救いを頷かせていただく身となることで、阿弥陀如来はその人をすぐに光明の中に摂め取ってくださいます。このことを阿弥陀如来の「摂取の光益」をこうむるというのです。また「不捨の誓益」にあずかるともいいます。このように阿弥陀如来の光明に摂め取られたからには、今生のいのちが尽きれば、ただちに真実の世界である浄土へと往生できることは間違いありません。このほかに阿弥陀如来以外の仏さまを拝んだり、また、念仏以外の功徳や善根を積む修行をしたりして何になるのでしょうか。阿弥陀如来の本願こそ、まことに尊く、この上なく有り難いものです。
この雨や山にたとえられる広大なご恩を、どのように報謝させていただけばよいのでしょうか。それは、ただ南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏のお念仏を称えて、そのご恩にこころから深く報いる他にはないと、心得ることであります。ああ有難や。ああ有難や。

「大聖世尊章」は蓮如上人が60歳、越前吉崎(現在の福井県あわら市吉崎)にお住まいだったころに綴られたお手紙です。
執筆日は文明6(1474)年8月18日とあります。前年の文明5(1473)年8月14日に蓮如上人の第4子(第2女)である見玉尼(けんぎょくに)が往生しているので、ちょうどその一周忌の頃でしょう。

帖外御文章(浄聖全5-p.247)に見玉尼のことが詳しく述べられています。
見玉尼は文明2(1470)年12月5日に伯母(内室蓮祐尼)を亡くし、文明3年2月6日に姉(如慶尼)を亡くし、度重なる死別が続いた後に自身もいのちを終えました。
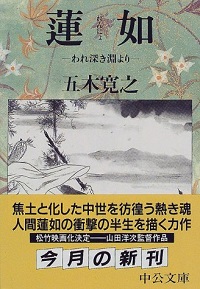
「大聖世尊章」を執筆された頃の蓮如上人は、愛別離苦の現実に直面し、その悲しみをこの一通に込められたのではないでしょうか。

章名の「大聖世尊」とは、お釈迦さまのことです。しかし、この「大聖世尊章」の内容はお釈迦さまが中心というわけではありません。特徴的な言葉をとらえて章名にしています。
本章の構成は次の通りです。
一 無常の様子を嘆ずる(それ、つらつら人間の ~ 無常なり。)
二 教えに遇うべきことを示す(しかれば、まれにも ~ 念仏申すべきなり。)
三 浄土真宗の教えを示す
(1)無信但称の異義を遮する(しかれば、世のなかに ~ おぼつかなきことなり)
(2)当流の正義を述べる
①六字の名号を釈す(されば南無阿弥陀仏と ~ おもふべきなり。)
②安心(信心)を示す(しかれば、この ~ ありがたの阿弥陀如来や。)
③信後の称名を示す(かやうの雨山の ~ べきものなり。)
この構成を一覧しても窺われますが、この「大聖世尊章」は『御文章』の総集編とでもいうべき、体系的な内容となっています。
このうち「三 浄土真宗の教えを示す」にあたる部分では「南無阿弥陀仏の六字の名号のいわれ」「信心正因・称名報恩の宗義」という浄土真宗の教えの綱要が、簡潔明瞭に示されています。

また注目されるのは、本章が「無常」を説くところから始められている点でしょう。無常を説く『御文章』といえば、「白骨章」が有名です。それ以外にも少なくありません。
本章では「無常」を通して「いま人間に生まれ仏法に出遇わせていただいているという事実が、いかに得がたく尊いものであるか」ということが分かりやすく教えられています。
私たちは普段の生活の中で、目の前にある幸せを「当たり前」と受け取り、その意味を見過ごしがちです。蓮如上人が「まれにも受けがたきは人身、あひがたきは仏法なり」と仰っていることも同様です。
「人間としていま生を受けていること」「仏法を聞く縁に遇っていること」、これらを「当たり前」と捉えがちな私たちに対して「いまの縁がいかに滅多にないものであるか」「いまの命がいかに儚く過ぎゆくものであるか」を述べておられます。

世間では「人間の前世は(過去の時代の)人間である」と考える人が多いようです。
しかし仏教では「人間に生まれる者は爪の上のわずかな土のようにごく稀であり、三悪道に堕ちる者は十方の世界にある土ほども多い」と説きます。
仏教で人間に生まれることの貴重さが繰り返し強調されるのは、「人間の世界は仏法に遇い得る縁の整った世界である」という大切な意味があるからです。
地獄や餓鬼の世界は激しい苦しみの連続で、教えを聞く心の余裕がありません。
もし目の前に仏法があっても、決して出遇うことはできないのです。
一方で、人間の世界も四苦八苦に代表されるさまざまな苦しみに満ちています。
しかし、その苦しみをただの苦しみで終わらせるのではなく、仏法に出遇う機縁として意味のあるものに転換していくことのできる世界でもあります。
源信和尚の作と伝えられる『横川法語』には
世の住み憂きはいとふたよりなり。このゆゑに人間に生れたることをよろこぶべし
と綴られています。

本章では「受けがたきは人身、あひがたきは仏法なり」というところから、さらに仏法のなかの聖道門・浄土門の区別を出されて、「しかるにいますでにわれら弘願の一法にあふことを得たり」と絞られています。
末代の私たちにおいては、この生死輪廻の世界を出離していくことのできる教えは、仏法のなかでも弘願の一法、すなわち、いま出遇っている浄土真宗の教えであるといわれるのです。
ここで蓮如上人は「弘願の一法にあふことを得たり」という表現をされています。
「教えにあう」「本願にあう」という言い方は「本願力にあひぬれば」のご和讃をはじめ、親鸞聖人も好んで用いられるものです。
『一念多念文意』に
まうあふと申すは、本願力を信ずるなり
と釈されていますように、「あう」は「信ずる」の同義語です。
しかし「信ずる」ということを「あう」ともいわれるところに大事な意味があるのではないでしょうか。
「あう」という言葉は人と人とが顔を合わせた時に使うことが多いです。ですから、「野菜にあう」「自動車にあう」とはあまり言いません。野菜や自動車との間には、人格的な交流がないからです。
ここから考えれば、浄土真宗の教えを「信ずる」=教えに「あう」といわれるのは、信ずることが阿弥陀如来という仏さまとのであいを意味しているからです。もちろんそれは「駅前で会う」というような物理的な出会い方ではありません。
世の中には物理的な出会いではなくても、遠く隔たっていても、その人の心に出会うということがあります。それは言葉を通して出会うという会い方です。

浄土真宗の教えを信ずるとは、南無阿弥陀仏の名号となって、またお釈迦さまのご説法となって、今ここに生きる私の元へと届いてくださっている阿弥陀如来のおこころに出遇わせていただくことです。
私という存在を「決して見捨てない」と丸ごと包み込んでくださる阿弥陀如来の智慧と慈悲に出遇わせていただくからこそ、今生の縁が尽きたときの往生成仏は今ここで必定のこととなります。このことを「信心正因」、また「現生正定聚」といいます。

そして、お念仏を申すことは尊いことですが、「とにかくお念仏したら往生できるだろう」という受け止めは、自分の行為ばかりを問題としていて、称えているお念仏そのものに込められた如来さまのお心をいただこうという態度ではありません。
だからこそ蓮如上人は「ただ声に出して南無阿弥陀仏とばかりとなふれば、極楽に往生すべきやうにおもひはんべり。それはおほきにおぼつかなきことなり」と仰っています。
六字の名号に込められた如来さまのお心を示されながら、そのおこころを素純に聞き信ずる信心のありさまを懇切に教えられているのです。
合掌