東京教区冬期僧侶寺族研修会が開催されました。

研修会の詳しい概要は先輩がブログにまとめてくださっています。
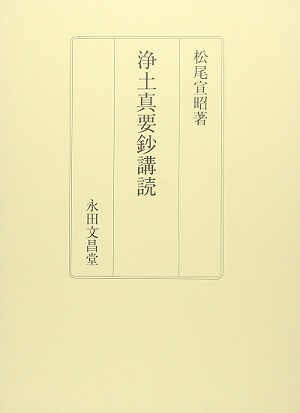
今回から研修会の講師選定に関わることになったので、松尾宣昭和上を推薦させていただきました。
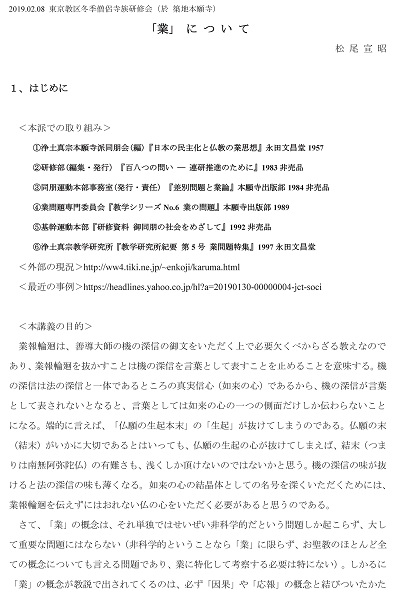
講題は事務局が決定した「業」について。
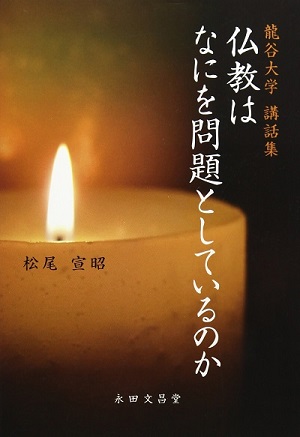
「地獄は一定すみか(業報輪廻)」も「弥陀の本願まこと(名号の救い)」も、ともに大願業力の活動相だということは、今回のテーマである「業」の問題にとって何を意味するか。最後にこの点について四つのことを押さえておきたい。
①
第一に、業報輪廻説はこのように大願業力の活動相であるのだから、業報輪廻の説意は、機が業報輪廻から出られない本質的あり方をしているからこそ救わずにはおかぬ法が立ち上がったのだ、と知らせることにある。
つまり厳しい真実を言わずにはおれないのは救うためであって、決して脅したり、貶したり、見下したりするためではない。
従って、業報輪廻説のお取り次ぎはあくまでもそこから救い出さずにはおかないという仏の慈悲を伝えるためになされるべきであって、たとえ取り次ぐ人に悪意がないとしても、結果的に受け取り手が脅された、貶された、見下されたと傷つくならば、仏意にそむくことになる。
『大経』五悪段をこの表現のまま今日取り次ぐことが許されないのは、この理由による。
②
第二に、業報輪廻説は先のように大願業力の活動相なのであるから、それは機の深信の内容であり、つまり如来よりたまわるものである。
しかも先に見たように私の業報輪廻的生存こそが仏願の生起なのであった。この仏願の生起については宗祖の有名な肉声が残されている。
弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとへに親鸞一人がためなりけり。さればそれほどの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ
これは「聖人のつねの仰せ」として記録されているもので、唯円の創作であるとは到底考えられない。
さて、この「それほどの業」とは弥陀に五劫思惟の願を思い立たせたほど底なしの罪業ということであるから、単なる自己反省ではなく、「親鸞を助けん」と思し召した大願が到り届いたことでもたらされた表現である。
つまり「それほどの業をもちける身」は機の深信の表現であり、つまり如来よりお聞かせたまわった機の真実である。
ということは、真実信心は「大願は私一人のためだった」と表現されるより他はないような境位において徹到する、ということになる。
この「聖人のつねの仰せ」を唯円はそのつど深い感動をもって聞いていたのであろう。
「親鸞一人がためと言われるからには、私は除外されるのか」といった疑問など一度も持たなかったことだろう。
真実信心をたまわる「一人」という境位は、決して他者を排除した境位ではない。
しかし他者を排除していないからといって、それが他者との連帯や社会的共存を意味するものではないことは「親鸞一人」と固有名詞まであげて強く仰ったことからみて明らかである。
もしそうでなければ、弥陀五劫思惟は「親鸞一人がためなりけり」ではなく「いしかわらつぶてのごときわれらがためなりけり」とでも言われたはずである。
他者を排除するのでもなければさりとて共存するのでもないような境位が他にあるかといえば、それはある。
それは「独生独死、独去独来」という境位、『御文章』で「まことに死せんときは、かねてたのみおきつる妻子も財宝も、わが身には一つもあひそふことあるべからず」と述べられている境位である。
これは妻子を始めとした他者を排除しているのではない。
いかに連れ添ってあげたいと思っても連れ添えない、「ただひとりこそゆきなんずれ」と言うしかない境位である。
蓮如上人が「往生は一人のしのぎなり」と言われたのはまさにここにおいてであって、決して自分さえよければいいといった倫理的利己主義を述べたものではない。
倫理は社会が成立するところで初めて意味をもつ。
しかるに「往生」すなわち「後生の一大事」とは、その社会と永訣していかねばならぬ「独死、独去」の境位について述べられた言葉である。
真実信心は、宗祖の表白の上にいみじくも示されているように、この「一人」という境位において徹到する。
よく指摘されることであるが、招喚の勅命は「汝、一心正念にして直ちに来たれ」となっているのであり、「汝ら」とはなっていない。
この信心の「一人」性はどうしても外せない。
この私一人を救わんとして五劫も思惟させたほど、それほどまでに果てしない罪業をもったこの身なのだという機の深信(業報輪廻の仰せ)は、従って私一人がうなだれて頂戴すべきものであって、あの人この人の話ではないのである。
③
大願業力の徹到による自力心の死を宗祖は「前念命終」とし、仏心を頂戴した正定聚として往生の道を歩むことを「後念即生」とされた(註釈版p.509)。
前念命終と肉体の臨終とがごく近い場合もあるけれども、大抵の場合は、前念命終と肉体の臨終との間に現世での生活期間がはさまっている。
つまり先ほどとは違って他者に連れ添える、寄り添える生活が存在している。
そこでは大願業力の徹到は自然と三業に現れる。典型的には五正行の助業(身業)と称名正定業(口業)の報謝活動であり、意業としては聞思や歓喜であるが、大願業力が徹到した以上、それは広い意味では生活全体に何らかの仕方で現れてくるはずである。
当たり前のことだが、行者は百パーセント大願業力の所成と化してしまうわけではない(そうなったら成仏したことになる)。
行者自身の宿業があり、様々な縁に応じての絶えざる三業の生滅がある。
それが大願業力とどのように絡み合い、その結果どのような果が生活の上で結ばれていくかについては全く分からないと言うしかないし、また各々の行者において千差万別であると言うしかない。
しかしながら、大きな文脈で見る限り、「一人」のためと頂かれた信心は称名を初めとする広讃略讃の大行となって(当人の意識からは報恩行だが)、十方衆生の上に弘く普く化していって「われら」と名乗る同朋を形成する、と宗祖がみておられたことは間違いない。
生死の苦海ほとりなし ひさしくしづめるわれらをば 弥陀弘誓のふねのみぞ のせてかならずわたしける
釈迦の教法おほけれど 天親菩薩はねんごろに 煩悩成就のわれらには 弥陀の弘誓をすすめしむ
釈迦・弥陀は慈悲の父母 種々に善巧方便し われらが無上の信心を 発起せしめたまひけり
五濁悪世のわれらこそ 金剛の信心ばかりにて ながく生死をすてはてて 自然の浄土にいたるなれ
等々、和讃であるから「われら」の立場で書かれてあるのは当然としても、後念即生の命が延ぶるなら、信心はおのずとこうした他者へのはたらきかけとなって展開する。
これもまた大願業力の活動相であり、信心の「われら」性と言える相である。
④
「一人」の相で徹到した信心を「われら」性の相として展開せしめていく大願業力の活動相は、しかしながら、われら念仏行者の三業とは無関係なのではない。
大願業力によって私は信心歓喜せしめられ合掌念仏せしめられるのであるから、人間他者に伝わる大願業力の活動相は、念仏行者の振る舞い方となるのである。
御門主が出された「私たちのちかい」はあくまでもこの局面で言われた言葉であって、決して賢善精進の励行ではない。
賢善精進の励行ではないけれども、怠惰に流れて他者へのかかわりに消極的になることを強く戒めておられる。
われらの悪業煩悩の本質は自他分別の上での自己中心性にあるのだから、放っておいたら本当に自分のことしか考えない。
信前の姿のままでは法を聞いた「しるし」がどこにあるのかと未信のひとから訝られて当然である。
そうなると結果的に御法を傷つけることになる。
それぞれの業縁に応じて自己の三業を律し、他者への働きかけへの努力を続けることが、われら真宗念仏者のつとめ、すなわちわれらの業でなければならないのである。

久しぶりにもの凄く充実した研修会でした。